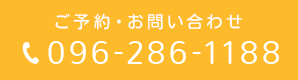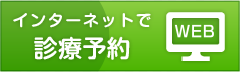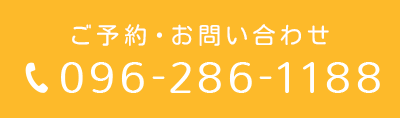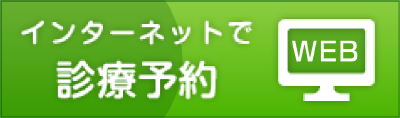コラム
認知症と歯との関係
日本が高齢化社会となり、徐々に問題として意識されるようになってきた認知症。
認知症の患者数は徐々に増加しており、2012年は462万人(高齢者の7人に1人)でしたが、2025年には推定650~700万人(高齢者の5人に1人)となるだろうと言われています。
この数になってくると、お身内に1人は認知症の方がいらっしゃる状態となり、決して他人事ではありません。
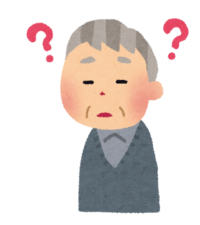
認知症は、記憶や認識、思考、判断力など脳の機能が障害され、日常生活に支障をきたす状態を指します。
特に多いアルツハイマー型認知症では「アミロイドβ」や「タウたんぱく」が脳に異常に蓄積されることが発症の一因とされていますが、なぜ蓄積されるのかはまだ解明されていません。
認知症が進行すると、介護が不可避になることが多く、老老介護やヤングケアラーなど家族にも大きな負担がかかります。

ここで見逃されがちなのが、口腔ケアと歯の健康も認知症予防にかかわるという点です。
噛む力や咀嚼は脳への刺激を与え、血流を促進することから認知症リスクの低減に繋がるとされています。
また、歯周病など口腔内の炎症が認知症に関与しているというデータもあります。
口腔内の炎症が慢性的に続いていると、全身の慢性疾患である高血圧や糖尿病が悪化しやすくなります。
これらが悪化すると、異常たんぱくの蓄積がおきやすくなります。また、脳血管障害による認知症が起きてしまう可能性も高くなります。
このため、定期的な歯科検診や日常の口腔ケアも重要です。
心身の不調を感じることが増える。仕事の予定や買い物などはスマホのリマインダーや付箋が欠かせず、時にはメモしたことすら忘れてしまうこともある。
こういった物忘れが気になる方は脳と口の健康を意識してみましょう。